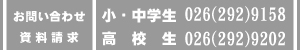ホトトギスはホーホケキョではありません
ホトトギスは ホーホケキョ と鳴きません。
ホーホケキョと鳴くのはウグイスですからね。
では、ホトトギスはなんて鳴くのでしょうか?
ホトトギスは テッペンンカケタカ と鳴くと言われています。

ホトトギスは、平安時代ではよく出てくる鳥です。頻度で言うならば、ウグイスなんかよりも数多く出てきます。そのくらい、なじみのある鳥だったんですね。
ところで、このホトトギスは5月から正式に鳴くと、当時は一般的に考えられていました。逆に言うと、4月にホトトギスの鳴き声が聞こえても、それは一般的な鳴き声ではなく、「人目を避けて隠れて鳴いている声」=「忍び音(しのびね)」と考えられていたのです。
平安時代の貴族の女性である和泉式部は、かつて為尊親王とお付き合いをしていました。ところが、この為尊親王が死んでしまうわけです。もちろん、和泉式部は悲しみにくれるわけですが、その後しばらくして、和泉式部は、為尊親王の弟である敦道親王と付き合うようになります。・・・はい、ちょっとアレですね。うん、これはマズいかな。・・・そういうわけで、和泉式部は人目を避けながら敦道親王とお付き合いをすることになるのです。
さて、お付き合いをはじめて数ヶ月たち、4月も終わりに近づきます。ところが、ここのところ敦道親王は、なかなか和泉式部の家に逢いに来てくれません。このまま人目を避けるような恋であるとしても、逢えないまま5月になっていくのは寂しいわけです。そんなとき、4月も終わりの最後の日に、和泉式部はこのような和歌を読みます。
ほととぎす 世に隠れたる 忍び音を いつかは聞かむ 今日も過ぎなば
四月も終わりである今日を過ぎ、五月になってしまったならば、ほととぎすが世の中から隠れてそっと鳴くような忍び音を聞くこともできません。同じように、今日を過ぎてしまったならば、忍び音のように、あなたは人目を避けて私の家にいつ来て下さるのでしょうか。今晩は、ぜひともおいで下さい。
平安時代は、恋をするにも教養が必要だたんですね~<(_ _)>