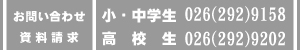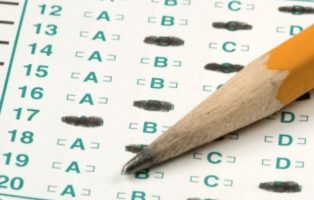
共通テスト後のスケジュール
共通テスト2日目が終了し、受験生にとって今夜は束の間の休息。
明日は、各高校で自己採点を行います。
なお、共通テスト明けのスケジュールを確認しておきましょう。
受験生 自己採点 1/17(月)
平均点 中間発表 1/19(水)
平均点 最終発表 2/7(月)
国立大学出願期間 1/24(月)~2/4(金)
国立大学前期試験 2/25(金)~
国立大学前期発表 3/6(日)~10(木)
国立大学後期試験 3/12(土)以降
国立大学後期発表 3/20(日)~24(木)
また、私立一般入試は大学によっては既に始まっているところもありますが、私立大学一般入試のほとんどが2月1週目~3週目が集中しています。
ちなみに、1/21(金)は得点調整の有無が発表されます。
得点調整が行われる可能性がある科目は以下の科目となります。
【社会科目】 「世界史B」「日本史B」「地理B」の間
【社会科目】 「現代社会」「倫理」「政治経済」の間
【理科科目】 「物理」「化学」「生物」「地学」の間
原則として、20点以上の平均点差が生じた場合、得点調整が行われます。
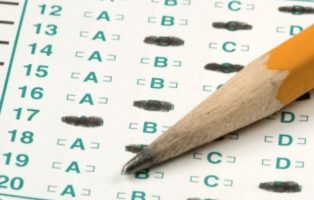
昨年度 共通テスト平均点
共通テストまでのこりあと3日。
昨年度の主な科目の平均点は、以下の通りでした。
国語 117.51点/200点満点
数学ⅠA 57.68点 /100点満点
数学ⅡB 59.93点 /100点満点
英語(筆記) 58.80点 /100点満点
リスニング 56.16点 /100点満点
物理 62.36点 /100点満点
化学 57.59点 /100点満点
物理基礎 37.55点 /50点満点
化学基礎 24.65点 /50点満点
問題数が多いため高得点を取るのはなかなか難しいですが、解ける問題で確実に点数確保することが大事です。
特に単純なケアレスミス(途中計算ミスや書き間違い、マークミス等)には注意したいものです。
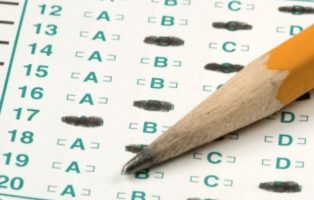
文部科学省 発表
1月11日(火)文部科学省発表
文部科学省は、新型コロナの感染拡大の影響で本試験も追試験も受けられなかった受験生のため、共通テストを利用する予定の国公私立の大学に、個別の入試の結果で合否判定するよう要請する方針を固めたことがわかりました。
「大学入学共通テスト」は、本試験は今週末の今月15日と16日に、追試験は今月29日と30日の日程で実施され、志願者数はおよそ53万人に上り、全国864の大学などの入試に利用される予定です。
さらに各大学の個別入試においても、追試験や振り替え受験の機会を得られなかった受験生のため、面接や小論文による「総合型選抜」などで再度の追試験の機会を新たに設けるよう要請するとともに、これにより入学時期が4月以降になることも可能にすると、全国の大学に周知する方針となるそうです。
共通テスト本番4日前の急な発表で、昨年度以上に今年の現役受験生は対応が難しくなるかと思います。
共通テストまで、残りあと4日。
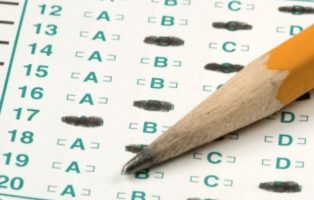
3学期開始
コロナの影響もなく、無事に冬期講習が終わり今週末から3学期授業がスタートとなりました。
ただ一つ不安なのが、新型コロナウィルスの変異株であるオミクロン株。
県外の一部高校では、来週の共通テストまで受験生の登校自粛し自宅学習に切り替えるところもあるようです。
また長野県のコロナウィルス感染者数も増加傾向にあり、いよいよ第6波が来たのかとそちらも不安です。
時習館では引き続き、館内でのマスク着用とアルコール消毒、換気等で感染対策を行っていきます。
来週末はいよいよ「共通テスト」が行われます。
ここで、共通テストの時間割を確認!
第1日目 1月15日(土)
9:30~11:40 社会(2科目受験型)
10:40~11:40 社会(1科目受験型)
13:00~14:20 国語
15:10~16:30 英語(筆記)
17:10~18:10 英語(リスニング)
第2日目 1月16日(日)
9:30~10:30 基礎理科
11:20~12:30 数学ⅠA
13:50~14:50 数学ⅡB
15:40~17:50 理科(2科目型)
16:50~17:50 理科(1科目型)

冬至
12月22日は「冬至」となります。
冬至とは24節気の一つで、1年のうち最も夜が長く、昼が短い日となります。天文学的に言うと、太陽が一番南に位置する日で、北半球では昼が短く、夜が最も長くなります。
「冬至」の別名は「一陽来復(いちようらいふく)」
「冬至」は中国や日本では太陽の力が一番弱まる日で、この日を境にしてパワーが甦ってくるため、冬至を境に運気が上昇すると言われています。そのため、この日にはかぼちゃを食べて栄養を付けて、体が温まるゆず湯に入り無病息災を願いながら寒い冬を乗り切ると良いとされています。
【24節気】
立春(りっしゅん) 2月4日頃
雨水(うすい) 2月19日頃
啓蟄(けいちつ) 3月5日頃
春分(しゅんぶん) 3月21日頃
清明(せいめい) 4月5日頃
穀雨(こくう) 4月20日頃
立夏(りっか) 5月5日頃
小満(しょうまん) 5月21日頃
芒種(ぼうしゅ) 6月6日頃
夏至(げし) 6月21日頃
小暑(しょうしょ) 7月7日頃
大暑(たいしょ) 7月23日頃
立秋(りっしゅう) 8月8日頃
処暑(しょしょ) 8月23日頃
白露(はくろ) 9月8日頃
秋分(しゅうぶん) 9月23日頃
寒露(かんろ) 10月8日頃
霜降(そうこう) 10月24日頃
立冬(りっとう) 11月7日頃
小雪(しょうせつ) 11月22日頃
大雪(たいせつ) 12月7日頃
冬至(とうじ) 12月21日頃
小寒(しょうかん) 1月5日頃
大寒(だいかん) 1月21日頃

ふたご座流星群
12月。
ふたご座流星群がピークを迎えます。
昨日、一昨日と夜空を見上げると流れ星を見られた方も多いことかと思います。年間三大流星群の一つである「ふたご座流星群」は12月がピークで、一晩に見られる流星数としては年間最大なんだそうです。時刻や条件が整うと一晩に500個近くの流星を見ることも出来るらしいですが、この寒空の下ずっと夜空を見上げるのはなかなか厳しいものです。
ちなみに今月12月19日は、今年最小の大きさになる満月が見られるそうです。
最小といっても月の大きさが変わるわけではなく、見た目が最も小さく見られるということで、見かけ上、今年最も大きく見えた満月は5月26日でした(月と地球の距離は約35万7000 km)でしたが、今回はその距離が約40万6000 kmと約5万kmほど遠くに見られます。
見た目が大きいと「おっ!大きい!」と感動するものの、見た目が小さい月は「おっ!小さい!」と感動しにくいのかもしれません。

積雪
11月下旬となり早朝深夜の気温が一気に下がり始め、白馬ではもう積雪が観測されました。
さて、本日11月24日は「鰹節の日」とのこと。
「い(1)い(1)ふ(2)し(4)」の語呂合わせから、鰹節のメーカー、ヤマキが制定したとことです。
ちなみ、魚繋がりで「2/14」は「バレンタインデー」で有名ですが、この日は「2(に)1(ぼ)4(し)」の日でもあります。これは、1994年に全国煮干協会が制定したもので、決して「バレンタインデーは中止になりました」と言いたかった訳ではないと思われるそうです。
魚と言えば、今年はサンマの値段が高く昭和時代のような庶民の魚ではなく、むしろ近年は高級魚の扱いになりつつあります。数年前までは1匹90円ほどだった価格が、今年は1匹150円ほどでなかなか買う勇気が出ず我が家でも今年はまだ1回しか食べていません。
ちなみにサンマの日もあるそうで、毎年「9月30日」だそうです。

第3回 中3ステップアップ講座
本日11/14(日)第3回中3ステップアップ講座を行いました。
今年からステップアップ講座は、3名限定の個別枠形態で実施し昨年度のクラス形態に比べより生徒の理解度に合わせた授業を行えています。
今回扱った数学の授業内容は「確率」
前回の第2回ステップアップ講座で扱った「順列・組合せ」計算を利用した問題演習を行いました。
前回参加できなかった塾生もいたり、前回内容を忘れている塾生もいたため授業最初は、再度計算方法の復習から行いました。計算はそれほど難しいものではないため、すんなり理解できたり思い出せたりした様子でした。
中には「ほぇ~」とか「へぇ~!」とか、その計算方法に感心する塾生もいました。
途中、コインの確率問題で「2の累乗」を確認しつつちょっとした雑学も話しましたが、そちらも興味津々のようでした。
なお、今回扱った計算方法は高校1年生で扱う「数学A」の内容ですが、中学生で十分利用できる計算方法でした。
次回第4回は12月に行う予定です。

高2共通模試
11/6(土)に高2共通模試を行いました。
現時点での共通模試に対する学力差を見ること、さらに共通テストのがどのレベルの問題でどのような出題のされ方なのかを知ってもらうことが目的でしたが、マーク形式のテストはなかなか解き慣れていないため、試験中も戸惑いがあったかもしれません。
でも、これも良い経験。
今の時点ではいろいろな失敗をして、その失敗した経験を次に生かしていけばいいと思います。
ご存知のように共通テストはマーク形式の試験で、普段の学校試験のような記述力よりはむしろより素早く問題文を読む、答えるといったスピード力が試されます。数学でいうと、途中式の組立方や、前半で出した解答や途中式の活用をするといった工夫が必要になります。高校2年生もあと数ヵ月でいよいよ受験生となるため、そういった工夫の仕方も今回の冬期講習内で行う「入試比較講座」で扱う予定です。

ティキ・タカ
前回からの続きというか、「新監督」の話題。
世界で有名なスペインのサッカーチーム、「バルセロナ」の新監督がチームOBの「シャビエル・エルナンデス・クレウス」に決まりました。現在41歳の彼は、バルセロナのカンテラ出身で1998年にわずか18歳でデビューした後、2015年までバルセロナでプレーしました。彼がもたらしたタイトルは数多く8度の国内リーグ制覇に加え、チャンピオンズリーグを4度も制覇するなど、バルセロナの一時代を築いたプレーヤーの一人です。同時期にチームメートだったイニエスタはJリーグのヴィッセル神戸へ、そしてメッシは現在フランスのパリ・サンジェルマンでプレーしています。(噂ではマルセイユとの契約が切れたらまたバルセロナに戻るような話もあるそうですが)
来年のバルセロナは、また彼が当時プレーしていたときと同じティキ・タカと呼ばれるショートパス主体のチームになるのか、それとも全く違ったロングパス主体のチームになるのか、今から楽しみです。
(ティキ・タカ)
ティキ・タカはショートパスをつなぎ、複数のパスコースを確保しつつオフ・ザ・ボールにおける選手の動きによってゴールへの道筋を作るプレースタイルと形容される。 このスタイルは、複数のパスコースを作りながらショートパスをつなぐ点と、辛抱強くパスを回し、保持したボールを失わないようにする点に集約される。
引用 ティキ・タカ – Wikipedia