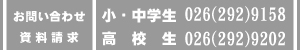春
今年度の授業ももうそろそろ終了し、3月下旬からは春期講習がスタートしていきます。高等部の春期講習は3/19スタートです。
→ 春期講習はこちらをクリック
ところで、この時期そろそろホームセンターなどでは「イチゴの苗」の販売が開始されます。毎年露地栽培でイチゴを育てていますが、ナメクジなどの食害がひどいため、今年はプランター栽培にしようと準備し始めています。
人類がイチゴを食するようになったのはかなり昔のことで、古代ローマ時代には何種類かのイチゴを栽培していたらしいです。日本では平安時代から食されていたようで、古代法典「延喜式」にはいちごの記載があり、野生のいちごが食ベられていたみたいですね。
でもなぜこれほどまでに日本人はイチゴが好きなんでしょうか。
これはどうやら「ビジュアル的な理由」が大きいようで、赤くて葉の緑とのコントラストが映える、切ると断面がハートなど見た目や形が可愛いといった理由らしいです。数年前にはオリンピック女子カーリング選手たちの「もぐもぐタイム」でも話題になったイチゴ。、これから先も日本人にとってのイチゴはデザートの主役であり続けるんでしょうかね。

啓蟄
先日、。3月5日(金)は「啓蟄」の日でした。
1年の春夏秋冬一年間を二十四分割したもののを「二十四節気」と言いますが、「小寒・大寒・立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至」とあります。有名どころでは春分の日や立春などが天気予報で耳にしますかね。
啓蟄とは、寒さが緩み春の陽気で暖かくなり、土の中で冬眠していた虫たちが動き出す季節のことを指します。
「啓」とは「ひらく」の意味で、「蟄」は土の中で冬ごもりをしている「虫」の意味。雪が融け春の気候になり始めたこの時期、もう雪は降らないと予想し、はやばやと車のタイヤ交換をしました。

春休み課題
3月になり、各高校では春休み中の課題が渡され始めました。
今のところ今年も昨年度と同等の課題量になりそうです。
屋代高校2年生の数学は、受験向けの問題集からの抜粋された問題プリントで少しばかり難しめ。一人で解くにはやや解きにくい問題もある様です。一応、解答解説も別紙で貰っているので、解けない問題はそれを利用していくと解けますが、途中式が省略されていたりすると困ってしまうかもしれません。そんな場合は自習ついでにぜひ質問しに来て下さい。この時期テストも終わり、自習座席が空いているので、ほぼ貸し切り状態で集中して自習可能です。

ホワイトデー
それは2月のバレンタインの日のことでした。
高校3年生から合格の報告とともに立派な義理チョコを貰いました。
というわけで、現在ホワイトデーに心ばかりのお返しをと、考え中です。
さて、ホワイトデーの起源については諸説あるようですが、
福岡市にある老舗菓子店の「 石村萬盛堂 」が最初のようです。
バレンタインデーのチョコのお返しとして「君からもらったチョコを僕のやさしさ(マシュマロ)に包んでお返しするよ」という意味を込めてチョコ餡を包んだマシュマロを1977年に考案したんだそう。
一方、全国飴菓子業協同組合が運営するホワイトデー公式サイトによると、ホワイトデーが生まれたのは1980年のことで、その2年前の1978年6月に、バレンタインチョコのお返しにキャンディーを贈る日として、全国飴菓子業協同組合が3月14日をホワイトデーと定めたそうです。
ちなみに、「ホワイト」は純血のシンボル、すなわち「純愛」の意味が込められているんだそうです。

卒業式
3月に入り、卒業式の時期となりました。
本日が卒業式の高校もあるようです。
外は残念ながら雨ですが、雨の卒業式もなかなか味わい深く良いものだと思います。
各高校のテストが2月下旬に終了し、自習座席利用者が少なくなり寂しい限りです。
ちなみにこの時期、自習座席がほぼ貸し切り状態。
貸し切り状態で勉強するなら今しかない!!
なお学習質問もお待ちしております。

国公立大学 前期試験
1月の共通テストが終わり、ほっとしている間にもう2月下旬。
いよいよ明日から国公立大学の前期試験が順次始まります。
時習館高等部では、先週までに2次試験向けの特別講座が一通り終わりました。
塾としては出来る限りのことは行い、受験生にとっても自信を付けた授業になったかと思います。
さて、今日からは受験生が各地へ移動ということになりますが、
移動中のマスク着用はもちろんのこと宿泊するホテルで体調を崩さないようにしてもらいたいところです。
国公立大学の前期入試合格は、3/6以降順次発表されていきます。

外壁塗装
2月に入り、時習館高等部校舎の外壁塗装の工事が始まりました。
駐車場内への車の乗り入れの際は、足場設置のため間隔が狭くなっておりますので十分ご注意下さい。
さて、共通テストも終わり国公立受験組の高校3年生は現在、集中して試験勉強に取り組んでいます。今週で国公立2次試験対策特別講座も終わり、いよいよ来週2/25に国立2次試験が開始されます。今年はコロナの影響もあり大学によっては急遽2次試験を中止にし共通テストの結果のみで合否を決めていくところもあります。国公立大学の前期入試合格は、3/6以降順次発表されていきます。
今年も多くの塾生が合格するのを願うばかりです

共通テスト
2021年が始まりました。
コロナの感染者数は増加傾向にあり未だ気を抜くことはできません。
さて、今週末はいよいよ「共通テスト」が行われますが、今年の大学入試は、センター試験から大きく変更となるため何が出題されるのか予想がなかなか難しく、平均点も下がると個人的には予想しています。
特に数学ⅠAは、試験時間が60分から70分に時間延長されましたが、その分問題文が長くなり、読解スピードも問われるため得点のばらつきは大きくなりそうです。

くつしたはつくした
12月になり、子どもたちが楽しみに待つクリスマスも近づいてきました。
うちの息子たちもクリスマスを楽しみにしており、サンタさんへの手紙を書いて、クリスマスツリーに飾り付けプレゼントを今か今かと楽しみにしています。
そんな息子たちの最近の言い間違い!?
「くつした」 → 「つくした」
「すべりだい」 → 「すべれりだい」
ん、ある意味間違いではないような気もする。

黒い銀
化学の個別授業のときのこと
生徒と「銀」の話題になりました。
銀って黒くなるんだよ、と。
銀のイオン化傾向はHg(水銀)の次でその値は小さく、酸化されにくい性質のはず。
そこで生徒が疑問を持ちました。「どうして?」
(解答)
銀が黒くなる理由は、「空気中の硫化水素と反応して硫化銀ができるため」
昔の銀食器や、シルバーアクセサリーが黒くなってしまうのは決して錆びたり酸化しているわけではなく、硫化銀(黒)ができ、それが表面に付着しているためです。ということは、硫黄(S)をそこから取り除いてあげればまたピカピカの銀色に戻せます。
手順と方法は?
まず、水に重曹を溶かして沸騰させ、黒くなった銀製品をアルミホイルなどのアルミ箔で包み込んで、重曹を溶かしたお湯に入れます。しばらくするとあら不思議。きれいな銀色に戻せます。
これは、高校化学で学ぶ「酸化還元」を利用したもので、銀よりはアルミニウムはイオンになりやすい(イオン化傾向が大きい)ため硫化銀がアルミニウムによって還元される反応が起きます。