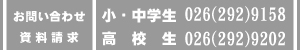数学 解答の表し方
数学の方程式問題で、次のような表し方をする生徒がいます。
9 x - 14 = 2 x
- 14 = - 7 x
2 = x
決して間違ってはいませんが、少しだけ違和感があります。
というのも、この方程式の主語は x であるので、
9 x - 14 = 2 x
7 x = 14
x = 2
の方が本来は見やすい形であり、解答としては綺麗です。
たしかに教科書には、特にこの形で書きなさいということは記載されていませんが、 「 x = 2 」という形の方が、採点する側にとっても見やすい形で印象も良いため、 出来る限り採点する側に立って解答を作るよう意識すると良いでしょう。

高校合格発表
今日は高校の合格発表日。
通常なら各高校の掲示板に張り出される合格発表者掲示を見て喜ぶところですが、今年はコロナ感染症のため自宅でインターネットを介して合格発表を見る受験生も多い様子。
コロナの影響だけでなく昨今、ネット通信の普及で実際に自分の目で各高校へ見に行く受験生も減りつつあるようです。
ネットの普及で便利な世の中になったものの、なんだか寂しさも感じられます。
そんな自分は、大学合格発表日にわざわざ大学のキャンパスまで見に行き、自分の受験番号を見つけたときのあの感動は今でも忘れることが出来ません。
巷では例年発表日当日、携帯ショップが大混雑するようですが今年はどうなんでしょうか。もしかしたらコロナの影響で当日のスマホ購入を控えるご家庭もあるかもしれません。

クッキー
昨日はホワイトデーということで
子供たちと一緒にクッキーを作りました
始めて作るにしてはなかなか上手にでき満足です
ところで、ホワイトデーは誰が考えたんでしょう?
ホワイトデーの起源については諸説あるようですが、
福岡市にある老舗菓子店の「 石村萬盛堂 」が最初のようです。
バレンタインデーのチョコのお返しとして「君からもらったチョコを僕のやさしさ(マシュマロ)に包んでお返しするよ」という意味を込めてチョコ餡を包んだマシュマロを1977年に考案したんだそう。
一方、全国飴菓子業協同組合が運営するホワイトデー公式サイトによると、ホワイトデーが生まれたのは1980年のことで、その2年前の1978年6月に、バレンタインチョコのお返しにキャンディーを贈る日として、全国飴菓子業協同組合が3月14日をホワイトデーと定めたそうです。ちなみに、「ホワイト」は純血のシンボル、すなわち「純愛」の意味が込められているんだって。

マーフィーの法則
何かをやろうとしたとき、いつも悪い方の結果が起きてしまうことって頻繁にありませんか?
「失敗する、ダメだ」 と思っていると、必ず失敗するという、いわゆるお約束。
======マーフィーの法則======
もともとは、ジョセフ・マーフィーによって一見逆説に聞こえるフレーズをことわざ風に表現したもの で、 日常生活で誰にでも起こりうる経験則をまとめたもの
「レジに並ぶと自分の並んだ列が一番時間がかかる」
「傘を持ってきたときに限って雨が降らない」
「計算間違いに気づいて、再計算したら今度は違う計算ミスをした」
「席を外した時に自分あての電話がかかってくる」
「二択問題で、自分が選んだ方が必ず外れる」
「病院へ行くと熱が下がる」
「学校宿題を頑張ったときに限って、宿題確認がされない」
「 トーストのバターを塗った面が下に向いて落ちる確率は、カーペットの値段に比例する」など
多くの人に当てはまる不思議な法則ですが、なぜ多くの人に当てはまるのでしょうか
一番しっくりくる答えは、おそらく「自己暗示」と「記憶の錯覚」
人は自己暗示により思ってもみない行動に出てしまうことが多々ありますし、また悪いことの方が記憶として残りやすいというのも原因の一つかもしれません
もし身の回りでそんな法則に出くわしたら、周囲の人と共感して楽しんでみるのも良いかもしれません

体調を崩してから食事が喉を通らず3日ほど断食中
水分だけはこまめに取るようにしていますが意外なことに空腹感はまだそれほどありません
これも普段からお腹にため込んだ脂肪のおかげか・・・
ところで、英語の「fast」という単語には「断食」という意味もあります
「断食」が終わった翌朝に食べる朝食は、断食が終わった後初めての食事となります。
すなわち、「断食(fast)」状態を「断ち切る(break)」とうことで
朝食のことを「breakfast」と呼ぶんだそうです
初めて知ったとき、なるほどとなりました。

昨日のこと
毎日自習に来るいつもの塾生2名が北海道大学の入試問題にチャレンジしていました
まだ高校2年生なのに結構解けていた様子で、少し驚きつつも来年度の大学入試ではかなり期待してしまいます
学校の長期休業でしかも部活動も禁止のため、時間を持て余しているようです
時間があるなら大学入試を解いてみようとするその姿勢、“意識”が高いです

人が感じる時間の長さは年齢が増すほど短くなることを、それを唱えたフランス人心理学者の名前から「ジャネの法則」と言うそうです。
心理学ではほかにも、「主観的時間の長さは年齢の3乗に反比例する」との考えもあるようです。
若いころに感じた長さとどう違うのか、計算してみて怖くなった
例えば、30歳の一日の主観的時間を24時間とすると、
10歳だと 27日
20歳だと 3日9時間
30歳だと 24時間
40歳だと 10時間7分
50歳だと 5時間11分
60歳だと 3時間
70歳だと 1時間53分
80歳だと 1時間16分
90歳だと 53分 でした
年を重ねるごとに、1日の主観的時間はどんどんと短くなっていきます。
計算するとより鮮明に自分に残された人生の時間もわずかなのだと気づけますが、願わくば主観的時間も考えずゆっくりとした時が流れるまま残りの人生を送りたいものです

ここ久しく雨が降っていませんが、雨は良いものです。
夏の時期、夕立後のアスファルトから立ち昇る雨の香りが好きな人もいるようです。
ところで英語にはこんな言い回しがあります。
It rains cats and dogs.
意味は、「土砂降り」
詳しい起源は不明ですが、どうやら単純に土砂降りの雨の音が犬とネコがケンカしている様にたとえられたのが起源らしい。なお英語以外のヨーロッパの諸言語では悪天候を「犬の天気」と言うようです。さらに面白いことに各国によっていろんな雨の言い方があるようでその言い回しもなかなかの秀逸。
イタリア 「洗面器となって降る」
フランス 「カエルが降る」
ノルウェー 「魔法使いのお婆さん(トロールイエリンガ)が降る」
スウェーデン 「小さなクギが降る」

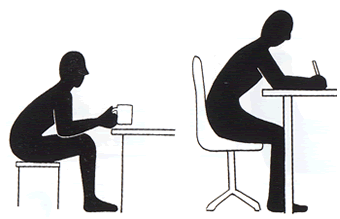
――――――――――――――――――――――
○○○○○○学習姿勢は正しいですか?
――――――――――――――――――――――
ここ数年の指導で気が付いたことがあります。
生徒たちを観察していて気付いたのですが・・・
「姿勢と学力は比例するということ」
成績上位者は、ほぼ全員がきちんとイスに座り、左手を添え、正しい姿勢で学習をしています。
さらに、左手で問題を指さし確認もしています。
一方、成績がイマイチの生徒は、机に向かう姿勢が悪く、左手も添えなかったり、目と机の距離が近すぎたりしています。
学力を上げたければ、なにはともあれ“姿勢を正すこと”ですね

今年もはやいもので2月中旬
しかも今日は男子諸君にとってはドキドキのバレンタインデー
そんな自分も塾生から手作りチョコを頂きました
お返しはゴディバのチョコが良いと言っていたけれども・・・
なるほど10倍返しということですか
ムムム・・・
バレンタインデーというと、女性から男性へチョコを贈り愛のプロポーズ的な日になっていますが、これは日本だけで本来のバレンタインデーは異なります。
時をさかのぼること、西暦3世紀頃のことです。
当時ローマでは、2月14日はすべての神々の女王ジュノーの祝日で、翌日の2月15日はルペカリアの祭りが行われる日でした。(ちなみにこの女神は結婚をつかさどる神で、結婚すると良い月と言われている6月(July)はこの女神の名前が由来です)
このお祭りでは、男性が桶の中から女性の名前が書かれている紙を引き、相手の女性と祭りの間パートナーとして一緒に過ごすことになっていたんだそうです。
そして、パートナーとなった多くの男女はそのお祭りで恋に落ち、結婚したと言われています。
当時のローマ帝国皇帝クラウディウス2世は、若者が戦争へ争いに行きたがらない理由は、「愛する家族や恋人を故郷に残すことを躊躇する気持ちにある」と言い、結婚禁止としてしまいました。
しかしこれを聞いたキリスト教司祭のウァレンティヌスはかわいそうな兵士たちのこと想い、内緒で結婚式を執り行いました。(そう、この人こそ、後にバレンタインと呼ばれる司祭様です)
そのことがやがて皇帝の耳にも入り、
怒った皇帝は法を無視したウァレンティヌスに罪を認めさせ、二度とそのようなことがないように命令しました。
しかし、ウァレンティヌスはそれに従わなかったため、処刑されてしまいます。
ウァレンティヌスの処刑日はジュノーの祝日であり、ルペカリアの祭りの前日である2月14日があえて選ばれました。
以降、毎年2月14日はウァレンティヌスが処刑された日として国民でお祈りをするようになったそうです。